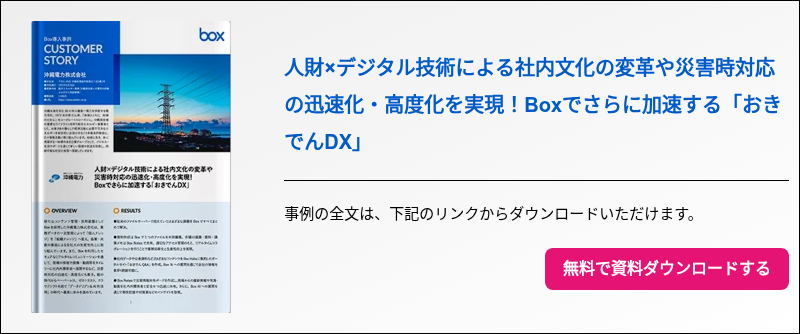人財×デジタル技術による社内文化の変革や災害時対応の迅速化・高度化を実現!Boxでさらに加速する「おきでんDX」
- 業種:電気・ガス・水道・エネルギー
- 企業規模:501名〜2,000名
- 課題:会議の効率化
- 課題:AIの活用
- 課題:情報共有の効率化・情報のサイロ化
- 製品名:Box AI
- 製品名:Box Hubs
従来のファイルサーバーで抱えていた運用・保守コスト、ITニーズの高まりによるコスト増、セキュリティリスク増などのさまざまな課題をBoxですべてまとめて解決
資料作成はBoxで1つのファイルを共同編集。会議の議題・資料・議事メモはBox Notesで共有。適切なアクセス管理のもと、業務効率化と生産性向上を実現
社内データや公表資料など、さまざまなコンテンツをBox Hubsに集約したポータルサイト「おきでんQ&A」を作成。Box AIへの質問を通じて会社の情報を素早く把握可能に
Box Notesで災害情報共有ボードを作成し、現場からの最新情報や写真・動画を社内外関係者と安全かつ迅速に共有。Box AIで現状把握や対策案などのインサイトを取得
沖縄本島を含む38の有人離島へ電力を供給する電力会社、沖縄電力株式会社。1972年の創立以来、「地域とともに、地域のために」をコーポレートスローガンに、沖縄県全域の重要なライフラインを担う総合エネルギー事業者として、お客さまの暮らしや経済活動に必要不可欠なエネルギーを安定的にお届けすることを基本的使命に、日々事業活動に取り組んでいます。地域に生き、共に発展する一体感のある企業グループとして、ビジネス・生活サポートを通して新しい価値の創造を目指し、持続可能な社会の実現へ貢献していきます。
新たなコンテンツ管理・活用基盤としてBoxを採用した沖縄電力は、業務データの一元管理によって「個人ナレッジ」を「組織ナレッジ」へ変え、協業・共創の推進による全社大の生産性向上に取り組んでいます。また、Boxを利用したセキュアなリアルタイムコミュニケーションを通じて、現場の情報や画像・動画等をタイムリーに社内外関係者へ展開するなど、災害時対応の迅速化・高度化にも着手。紙の時代からペーパーレス、ゼロトラスト、クラウドシフトを経て「データドリブン&AI利活用」の時代へ着実に歩みを進めています。
2025年度経営方針に記した“Box導入”
「総合エネルギー事業をコアとして、ビジネス・生活サポートを通して新しい価値の創造を目指し、地域に生き、共に発展する一体感のある企業グループとして、持続可能な社会の実現に貢献します」。2022年3月に発表した「おきでんグループ 中期経営計画2025」でこのようなビジョンを示した沖縄電力は、これまで「トップラインの拡大」、「攻めの効率化」、「カーボンニュートラルへの挑戦」を推進し、エネルギープラスαの新たな価値の提供に取り組んできました。
2025年4月に発表した2025年度経営方針では、喫緊の課題である物価高対策として立ち上げた「おきでんPXプロジェクト」において、基本的使命である「安定供給」を大前提に調達活動の変革・コストの最適化・生産性の向上・更なるスキル向上を強化すべく、自ら工夫して仕事のやり方を変える「超・攻めの効率化」により、前例にとらわれない変革にグループ一丸となってChallengeしていくことを宣言。その実現に向けたコーポレート部門・全部門横断の取り組みでは「DX人財育成」ならびに、Box導入による「先進テクノロジ活用による業務変革」と「ナレッジ活用によるDX推進」を掲げています。
「Boxを導入することで、『いつでもどこでもコミュニケーション・コラボレーション』『必要な時に必要なデータをすぐに活用』『ビッグデータと生成AIで新たな価値創出』『災害対応の迅速化・高度化』『人材×デジタル技術によるビジネス刷新』を実現することを目指しました」(DX推進事務局長 仲間博文氏)
なぜ今Boxを導入するのか?
沖縄電力でBoxの導入に至ったのは、デジタル化・ペーパーレス化が浸透し、ゼロトラスト基盤の構築によってクラウドサービス活用を促進するIT環境が整ったものの、DX推進を阻害するさまざまな課題が社内に存在していたからです。
「会社で紙を使うことはなくなり、社内はすっきりしたのですが、データ空間は別でした。さまざまなツールにファイルが散在し、バージョン管理も煩雑で探し出すのに時間を要していました。また、毎回暗号化が発生するパスワード付きのメールでのやりとり(PPAP)や、ファイル単位での活用が主で膨大なデータを日常的に活用できていないこと、同時編集が行えないことなどにも課題を抱えていました。さらには、ファイルサーバーの運用・保守コスト、ITニーズの高まりによるコスト増、セキュリティリスク増にも悩まされていました」(仲間氏)
電力会社としてもう1つ重要だったのが、従業員の行為規制も考慮した厳格なファイル管理への対応でした。沖縄地域は本土から独立した単独かつ小規模な電力系統であることから、弾力的な電源運用と災害対応のために送配電部門、小売部門および発電部門が一体となって電気事業を行うことが許可されています。しかし、兼業認可を得ていても、送配電部門には中立性の確保が求められます。
「そのためには会社の中でアクセス権を厳格にコントロールしなければなりません。これまでは人事異動時などに生じるアクセス権の付与を手動で行っていたため限界がありました。情報バリアをしっかりと構築できることもBoxを選択した決め手の1つです」(仲間氏)
Box導入で実現する働き方改革
沖縄電力ではこうした課題を一気に解決するために、2025年1月にBoxの採用を決定しました。ファイルサーバーやバックアップ、大容量ファイル転送サービス、システム運用・保守、セキュリティ対策、電子契約サービスという現行コストに、将来投資が必要となるコスト(HS/SW更新、ストレージ容量追加、マルチデバイス対応、脱パスワード付きメール、電子帳簿保存法対応、文書管理基盤整備、高度セキュリティ対策、生成AI活用基盤整備、システム・アプリ間連携、先進テクノロジ活用)を加えるよりも、それらを1つですべて賄えるBoxを導入するほうが費用対効果が高いと判断した結果です。そのうえで生産性向上や働き方改革、DX推進、セキュリティレベルの高度化、複数システムへの投資抑制などに期待できることも高く評価しました。

「『いつでもどこでも誰とでも』『情報を自由に繋げてまとめられる』『AIなどの高度な最新機能を使える』という大きな特徴を備えたBoxはもはや単なるツールではなく、会社の文化を変える仕組みです。部門の壁や役職の壁、会社の壁など社内にはさまざまな壁が存在しますが、それらは本当に必要でしょうか。こうした壁が存在すると情報共有やコミュニケーションが煩雑で非効率になります。Boxというハンマーでその壁を打ち壊し、『フラットでクイックに!』という環境を構築することが大切です。適切なアクセス管理のもと、さまざまな情報に対して迅速かつ安全にアクセスし、コミュニケーションを通じて素早く決断する。そうした壁のないスムーズな業務環境がBoxによって整いつつあります」(仲間氏)
沖縄電力では2025年2月より従来のファイルサーバーからBoxへのデータ移行を開始し、2026年4月以降のファイルサーバー撤廃を目指して、コンテンツ管理・活用の基盤を完全にBoxへシフトさせていきます。将来的には10社以上あるグループ全体にも展開し、グループ大でのDX推進をさらに加速していきます。
個人ナレッジを組織ナレッジへ変える
Boxに期待した「フラットでクイックに」という導入効果は、日常業務のさまざまなシーンで見え始めています。たとえば資料作成において、これまでは、担当者による素案作成→部内確認→関係部署・関係会社確認→担当役員承認という一連のプロセスによって情報共有に時間を要し、手戻りが生じるケースもありました。担当者には「資料を見てくれているのか」という不安、確認者には「資料が上がってこない」という不安が生じることもあります。Box導入後は資料をBoxに格納して共有するだけで関係者全員が同時にいつでもどこでもスマホでも確認可能に。バージョン管理機能を利用して1つのファイルにどんどん修正やコメントを重ねていくことで、作業効率が格段に向上しました。
「このように業務データをすべてBoxで一元管理して適切なアクセス管理を行い、リアルタイムコラボレーションを行えば、個人のナレッジを組織のナレッジとして持続的に活用できるようになり、グループ大の生産性向上を期待できます」(仲間氏)
Box導入後に大きく変わったのが会議です。これまでは会議前にファイルサーバーなどに格納した議題や資料を探し出して確認し、会議中は参加者各自がバラバラにメモを取り、会議後に担当者が議事録を作成して関係者に確認し、配布するというスタイルでした。Box導入後は会議前に議題や資料をBox Notesに貼り付けて共有。参加者はそれを見ながら内容確認や事前準備を行い、会議当日はすぐに本題へ入ることで会議品質と生産性の向上、時間短縮を実現。議事メモは会議中に参加者がBox Notesを同時編集してその場でまとめることで、参加者は会議後に次のアクションにすぐに着手できるようになりました。
このような「ドキュメントDX・ミーティングDX」を実現できた背景には、Boxを単に導入しただけでなく、Box全社活用に向けて沖縄電力のIT部門が地道に行った定着化・利活用促進の取り組みがあります。
「沖縄電力では約85%もの従業員がBox Notesを利用しています。全社向けウェビナーや掲示板を利用した情報発信だけでなく、沖縄本島や宮古、八重山、東京支社や各発電所など、各拠点に直接訪問して説明会を実施したことがこの高い利用率に繋がっていると思います。また、『シリーズ1日1歩1Box』と題してBox活用に関連する情報を日々ポータルサイトで発信し、ITを得意としない従業員を取り残さないように優しく寄り添ってサポートしました」(仲間氏)
Box AIが災害時対応に威力を発揮
沖縄電力ではBox AIの活用も進んでいます。その一例として挙げられるのは、Box Hubsを利用して作成した「おきでんQ&A」です。社内データや経営方針・統合報告書といった公表資料、社内報など、さまざまなコンテンツをBox Hubsに集約したこのポータルサイトでは、従業員が会社の情報を素早く検索できるだけでなく、「当社のカーボンニュートラルの取り組みは?」などとBox AIに質問することですぐに回答を得られます。
「株主総会の際に役員が参照するQ&AポータルサイトもBox Hubsで作成しました。これまで役員は分厚いファイルを持ち歩いていましたが、さまざまな部門が作った想定Q&Aを集約したBox Hubsを活用し、Box AIへの質問を通じて回答に必要な情報を得ることができました」(仲間氏)
Box AIとBox Notesの組み合わせは、災害時対応の迅速化・高度化にも効果を発揮。災害が発生した際は経営層を含めて素早く現場の状況を共有して対策を講じる必要がありますが、この際にBox Notesの災害情報共有ボードを通じて各現場からの最新情報や、スマートフォンで撮影した写真・動画を社内外関係者と迅速かつ安全に共有しています。
「例えば各現場の状況や道路の閉鎖情報などを書き込んでおけば、Box AIへの質問を通じて現状把握や対策などのインサイトをすぐに取得できます。また、過去に行った総合防災訓練のデータをBoxに保存し、“昨年の訓練を踏まえた今年の改善点は?”のようにBox AIに尋ねれば、改善策を提案してくれます」
また、ボタン1つで呼び出すことができるBox Notesのカスタムテンプレートの作成も行い、災害時などにその共有リンクを関係者に送信することで、あらかじめ作成した項目に従って関係者が素早く各種情報を書き込み、共有できるようにもしています。

「Box NotesとBox AIは、教育にも活用できると思っています。たとえば、各種業務資料や役員説明資料、社内外発表資料、ベンダー資料等をBox Notesに集約すれば従業員の資料作成時や各種調整時などに役立つだけでなく、新入社員や転入社員のための教育コンテンツとしても活用できます。部署の業務内容をBox Notesに保存して更新すれば、配属された部門の仕事が見渡せます。もちろん人に聞くのもいいのですが、いつでも気軽に使えるのでとても便利です」(仲間氏)
沖縄電力では既にAIチャットを全社へ導入していましたが、その活用が全社員へ浸透していたわけではありませんでした。
「いくらAIエンジンが優れていても、インプットするデータが充実かつ適切でなければAIは威力を発揮できません。 その点、Box AIはBox上に保存した膨大かつさまざまな種類の自社データ群に対し、厳格なアクセス管理のもと、AIチャットを通じて質問や情報検索、要約、分析が行えます。たとえば、Box Notes上の情報に基づいて顧客向けの新規サービスを提案してもらったり、現場向けの教育プランを提案してもらったりなど、従業員のさまざまな日常業務に効果を発揮します。今後はプロンプト教育を実施し、従来のファイルサーバーのBox移行が完了次第、全従業員での日常的な生成AI活用を目指していきます」(仲間氏)