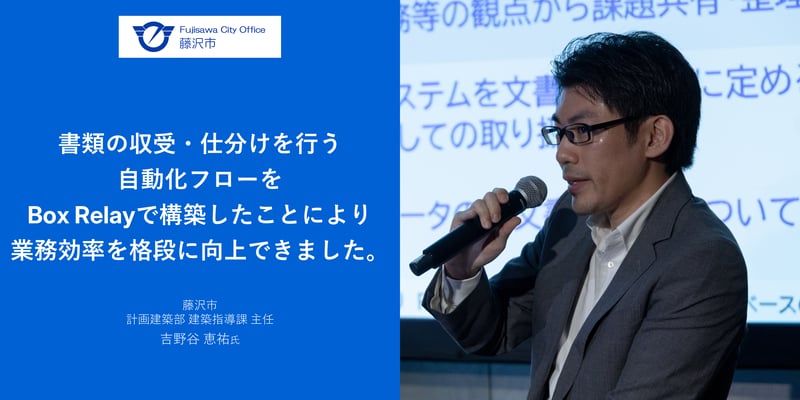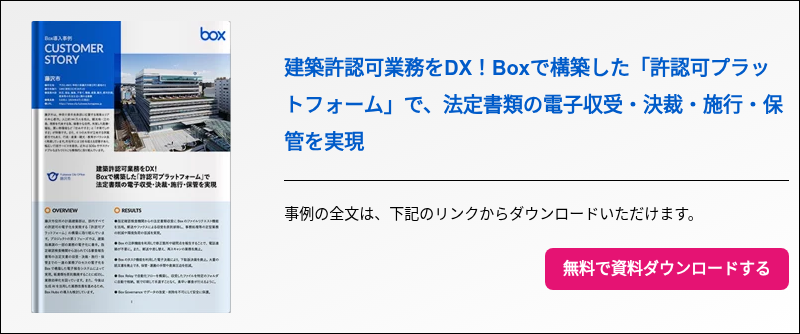建築許認可業務をDX!Boxで構築した「許認可プラットフォーム」で、法定書類の電子収受・決裁・施行・保管を実現
- 業種:政府・官公庁・自治体
- 企業規模:2,001名〜5,000名
- 課題:ペーパーレス化
- 課題:業務プロセスの自動化・効率化
- 課題:DX推進
- 製品名:Box Relay
- 製品名:Box Governance
- 製品名:Box Hubs
指定確認検査機関からの法定書類収受にBoxのファイルリクエスト機能を活用し、郵送やファクスによる収受を原則排除
Boxの注釈機能を利用して修正箇所や疑問点を報告することで、電話連絡が不要に。また、郵送や差し替え、再スキャンの業務を廃止
Boxのタスク機能を利用した電子決裁により、下駄版決裁を廃止。大量の紙文書を廃止でき、保管・運搬の手間や倉庫圧迫を低減
Box Relayで自動化フローを構築し、収受したファイルを特定のフォルダに自動で格納。紙で印刷して手渡すことなく、審査を迅速化
藤沢市は、神奈川県中央南部に位置する湘南エリアの中心都市。人口約44万人を抱え、観光地・江の島、湘南を代表する海、緑豊かな自然、充実した医療・福祉、買い物環境など「住みやすさ」と「子育てしやすさ」が特徴です。また、4つの大学が立地する学園都市でもあり、行政・産業・観光・教育がバランス良く発展しています。市役所には100を超える部署があり、幅広い行政サービスを提供。近年はSDGsやサスティナブルなまちづくりにも積極的に取り組んでいます。
藤沢市役所の計画建築部は、部内すべての許認可の電子化を実現する「許認可プラットフォーム」の構築に取り組んでいます。プロジェクトの第1フェーズでは、建築指導課の一部の業務の電子化に着手。指定確認検査機関から送られてくる審査報告書等の法定文書の収受・決裁・施行・保管までの一連の業務プロセスの電子化をBoxで構築した電子報告システムによって実現。紙書類を原則撤廃することに成功し、業務効率化を図っています。また、今後は生成AIを活用した業務改善を進めるため、Box Hubsの導入も検討しています。
「許認可プラットフォーム」の実現に向けて
制度や組織のあり方をデジタル化にあわせて変革するDXが社会的に求められる中、藤沢市は「これまで地域で育まれてきたコミュニティ」「官民連携など多様な主体によるパートナーシップ」「デジタル技術やAI等を活用したテクノロジー」の3つの視点から、市民一人ひとりのニーズに合ったサービスを提供し、「だれもが安全安心で生き生きと暮らせる藤沢市」への変革を進めるために、2021年4月に「デジタル推進室」を新設しました。また、2025年4月にはデジタル推進室と情報システム課を統合して「デジタル戦略課」へ組織改正するとともに、2024年4月に策定した「藤沢市DX推進計画」の改訂を行い、策定当時に定めたKPIの達成状況や今後の取り組みなどについて公開し、新しいまちづくりに向けたDXを推し進めています。
この「藤沢市DX推進計画」にはさまざまな取り組みが盛り込まれていますが、その中で最重要取組項目の1つに設定されたのが、既存サービスや個別に作成されたシステムを自動的につなぎ合わせて行政のデジタル化を推進する「デジタルプラットフォーム」の構築です。具体的には、総合問い合わせ窓口「コンタクトセンター」の開設や市民向けのポータルサイト「ふじまど」の充実に加え、事業者向けポータルサイトとして「許認可プラットフォーム」を構築することが大きな戦略として掲げられました。
許認可プラットフォームは計画建築部の発案から生まれたDXプロジェクトで、部内すべての許認可の電子化を実現し、地域住民や事業者などが来庁することなく、あらゆる許可申請を可能とするものです。計画建築部ではこの全国に類を見ないプロジェクトの実現に向けて業務課題を整理し、3つのフェーズに分けてプロジェクトを設計。まずは建築指導課の一部の業務のDXを行うため、2025年を目標に法定書類の電子報告システムの構築を開始しました。
大量の紙書類の処理が大きな業務負担に
計画建築部が電子報告システムの構築で目指したのは、市内で建築される物件の法定書類の電子化を実現すること。建築物の建築前後には建築主事や指定確認検査機関によって法律で定められた基準に適合しているかが審査されますが、神奈川県内では認可を受けた民間の指定確認検査機関(39機関)が9割以上の審査を行っています。その結果、指定確認検査機関から審査報告書等が“紙”で送られてくることが大きな業務課題となっていました。
「年間約2200件の新築に対して8000件/年以上の審査報告書等(紙にすると約16万枚)が郵送またはファクスで届けられ、開封や仕分け、システムへの取り込みなどの処理が業務を圧迫していました。審査報告書等を電子データとして送付できる電子報告システム(ICBA:通知配信報告システム)は存在するものの、対応する指定確認検査機関は全体の約4割で、件数にすると約30〜50%程度。事務処理等の軽減に寄与しているとは言い難く、紙と電子が混在してしまうので逆に手間が増えてしまうという課題もありました」(計画建築部 建築指導課 主任 吉野谷恵祐氏)
さらには電子収受した書類を印刷して保管したり、書面収受した書類をスキャンして電子台帳に手入力で登録し、証明書として発行できるようにテキストデータに変換したりするなど、電子から紙、紙から電子にデータ変換・出力するという非効率な業務が発生していたことも課題でした。
そこで計画建築部では、情報セキュリティの観点から課題共有・整理を行い、その他業務のオンライン化に向けて各種ツールとの連携も視野に入れながら、民間のクラウドストレージの運用可否の分析を開始。また、審査報告書等の一連の業務プロセスを可能な限り省力化し、県内統一を図るために、公文書事務等の観点からも検討を行い、文書管理規定に定める文書管理システムとしてクラウドベースの承認システムを利用できないか、電子データとして公文書として保管できないか等の検討も行いました。
「指定確認検査機関とのデータ収受を実現することで郵送やファクスによる収受を原則排除し、事務処理等の定型業務の減少や環境負荷の低減を目指すだけでなく、電話による修正依頼、昔ながらの下駄版決裁、倉庫を圧迫する大量の紙文書の保管などもまとめて一気に解決したいという思いがありました」(吉野谷氏)
そして、こうした要件を満たすソリューションとして、容量無制限で利用できる点や、ISMAPに登録されていて安全に利用できる点などを評価してBoxを採用したのです。

Box導入によってもたらされたメリット
Boxで構築した電子報告システムでは、Boxのファイルリクエスト機能を利用し、Boxのアカウントを持っていなくても、送られてきたリンクをクリックしてファイルをアップロードするだけで簡単に書類を送付できるようにしています。
「相手側に初期コストや運用コストがかかってしまうと、結局使われなくなる可能性があります。しかし、ファイルリクエストならば無料で利用でき、郵送コストや時間ロスを抑制できます。建築指導課としても年間8000通ほど届いていた郵便物の開封作業やスキャン作業などの事務作業を廃止できたほか、電子データで収受できるのでその後の作業も楽になりました」(吉野谷氏)
また、指定確認検査機関への修正箇所や疑問点などの連絡にはBoxの注釈機能を活用することで、1回3〜5分程度かかる数百件の電話連絡が不要に。Boxのバージョン管理機能を利用すれば履歴を遡って修正内容を確認できるため、郵送や差し替え、再スキャンの業務も廃止できました。
さらに電子報告システムでは、Boxのタスク機能を利用した電子決裁を導入し、従来の下駄版決裁を廃止して起案作成時間の短縮を実現しています。その結果、大量の紙文書を廃止することができ、倉庫への運搬・保管などの保管業務の短縮、倉庫の圧迫軽減にもつながりました。Boxに保管するデータはBox Governanceの機能を利用して削除を不可にし、安全に保護しています。
Box Relayで書類の自動収受・仕分けを実現
電子報告システムでもう1つ特筆すべきなのは、Boxのフォルダ機能やメタデータ機能、ならびにワークフロー機能の「Box Relay」を利用して、審査報告書等の自動収受・仕分けの仕組みを実現した点です。
藤沢市では「αモデル」を採用することから、「LGWAN-ASP」サービスを利用して職員ポータルやLGWAN接続系システムから直接Boxを開けるようにしています。そのためBoxのフォルダ設計に関しては情報漏洩等の懸念を考慮し、「建築指導課(外部共有)」と「建築指導課(内部)」「建築指導課(公文書保管)」という3つのフォルダを用意。「建築指導課(外部共有)」は外部ユーザーを招待できる一方で、一般職員はファイルのアップロードを不可に設定。また、職員によるファイルの保存や作成が可能な「建築指導課(内部)」は原則として課の所属者のみ閲覧可能とし、招待を行うことで庁内での共有を可能にしています。さらに「建築指導課(公文書保管)」はビューワーのみの権限として改変ができないように制御してセキュリティを担保しています。
こうしたフォルダ設計を行ったうえで、Boxのメタデータカスケードポリシーを使用してフォルダ内のファイルにメタデータを自動付与したり、ファイルリクエストで送ってもらうときに送信者情報を入力してもらったりすることで、ファイルを自動的に該当するフォルダへ格納するワークフローをBox Relayで構築。「建築指導課(外部共有)」フォルダにある「指定確認検査機関(収受用フォルダ)」内の指定したフォルダにファイルリクエストでファイルがアップロードされると、その配下に識別番号が付与された引受収納用フォルダが作成され、「識別番号+引受」という名称に変更されたファイルが格納されます。その後、引受収納用フォルダとファイルは相手への指摘書き込み用の「収受済」フォルダへ移動され、同時に「建築指導課(内部)」フォルダ領域内の「引受報告書(処理中)」にコピーされて格納。その後、必要データが添付されると、建築指導課フォルダや関係各課共有フォルダに自動で振り分けられます。このような自動化フローの仕組みを整えることで、ファイルが自動的に必要な場所にソートされ、紙で印刷して手渡さなくても素早く審査が行えるようになりました。
Box Hubsで過去の知見を集約してナレッジ化
このようにBoxを利用した電子報告システムを構築することで法定書類に関する業務のDXを見事に実現した建築計画部ですが、その成功の裏には単にシステムを導入するだけではなく、そのメリットを理解してもらうために庁内および外部のさまざまなステークホルダーと地道に折衝を重ねた努力があります。
たとえば、財政部局との協議では、Boxの導入費用だけでなく、現場にどれだけ“ムダ”があるか(削減できる費用と業務時間)という時間と物品のコストをしっかり見直すことによる電子報告システムを導入した際の効果を説明。総務・文書管理部局との協議においては、Boxによる文書の電子化が総務・文書管理部局にもたらすメリットを説明。共感が得られるまで何度も話を重ね、文書取扱規定を改訂しました。もちろん、Boxを導入したからといって使ってもらえなければ意味がないことから、指定確認検査機関との協議においても課題を整理しながら、お互いの落とし所を粘り強く探っていきました。
「ファイルリクエストの機能が無料だからといって、必ずしも使ってもらえるわけではありません。指定確認検査機関は藤沢市だけでなく、他市や他県の業務も行っているため、藤沢市だけのために業務を変えて、従業員に教育を行うのは難しいという声をいただいたこともあります。しかし、どこかが始めなければその後の広がりはないため、まずはICBAを使っていない指定確認検査機関を中心に折衝を重ね、6社から試験運用を開始しました。現在では審査報告書の85%を電子報告システムで授受しています。また、スケールメリットを最大化させるために関係自治体にも協力を依頼し、鎌倉市と茅ヶ崎市にも開始いただくほか、そのほかの市でも検討されています」(計画建築部 建築指導課 課長補佐 相川琢氏)
建築計画部では今後、建築指導課のすべての申請の電子化の実現する電子申請システムの導入(フェーズ2)を2028年までに、計画建築部のすべての許認可の電子化を実現する許認可プラットフォームの構築(フェーズ3)を2030年までに進めていきます。
また、藤沢市に限らず、現在は公務員の成り手不足(特に技術職員不足)が深刻である現状を踏まえ、もはや業務改善の先延ばし不可能と捉え、業務を回していくためにDXによる積極的な業務改善を図っていきます。そのための取り組みの1つとして、現在は生成AIを用いた回答の生成実証実験を行っていますが、書類の電子化が進んでいないため、回答の精度が低いことが大きな課題となっています。
「その解決に向け、建築基準法や参考資料、Box Notesで作成した審査担当会議記録をまとめ、AIが適切な回答を生成できるようにBox Hubsの導入を検討しています。これが実現されれば、たとえば人事異動によって失われていた知識・経験などをAIに肩代わりしてもらい、次の世代に繋げていけるのではないかなと思います」(吉野谷氏)