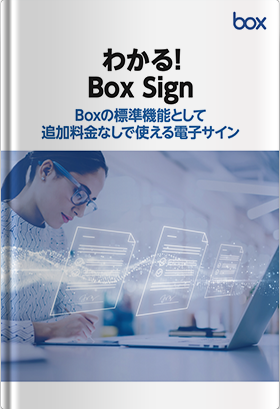行政の届け出や企業の取引など、さまざまな場面でハンコの押印を不要とする「脱ハンコ」が進められています。しかし、ハンコ文化を変えるにはさまざまな困難が伴い、なかなかスムーズに移行できていないのが現状です。
そこで本記事では、脱ハンコを国が推進する経緯と脱ハンコを阻んでいるものは何かについて解説します。そのうえで、脱ハンコへのプロセスとして重要な文書を電子化する方法、効率的に脱ハンコを推進するために役立つツールなどについて紹介します。

脱ハンコとは
脱ハンコとは、従来契約書の締結や請求書の発行、金融機関・行政サービス等での手続きに必要とされた押印を廃止するための取り組みです。手段としては、必要がないハンコの押印を取りやめること以外に、文書を電子化したうえで押印作業またはそれに代わる署名等を電子的に行う方法もあります。
2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い緊急事態宣言が発令された際には、書類に押印するために出社する人が少なくないことから、押印文化がテレワークを阻害するため廃止すべきだという議論が活発化しました。河野内閣府特命担当大臣の脱ハンコについての記者会見やGMOインターネットグループがいち早く押印廃止を決定したのに続き、サントリーでは押印業務を電子化するなど、徐々に脱ハンコの動きが民間企業だけではなく、中央省庁・自治体も含め官民での動きとなっています。
関連内容はこちら
脱ハンコ推進の経緯と政府の動き
世の中が大きく脱ハンコへと舵を切った背景には、行政のDXを推進する動きもあります。2021年9月にはデジタル庁が発足し、DX推進の施策を迅速かつ重点的に実施し、デジタル社会の形成を目指しています。
政府は、デジタル時代を見据えて書面主義、押印原則、対面主義からの決別を解決すべき課題と位置づけ、民間から行政への手続きに対して認印はすべて廃止、他の押印についても99.4%が廃止または廃止の方向とすることを表明しました。2020年12月には、この動きを地方公共団体でも推進すべく「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を公表し、脱ハンコを広く進めています。
関連内容はこちら
署名・押印を廃止することで、従来紙で運用していた各種書類のペーパーレスが促進されます。電子ファイルで管理する際には、発行元のなりすましや文書の改ざんを防ぐ必要があり、電子サインやタイムスタンプ、eシールといった認証技術が取り入れられています。
タイムスタンプとは、ある時刻に該当のデジタルデータが存在し、またそれ以降改ざんされていないことを証明する技術です。時刻認証事業者にタイムスタンプを付与してもらうことで、文書の非改ざんを証明できます。eシールは、文書の発行元を証明する目的で利用される暗号化技術です。認証局が発行元の実在を証明した電子証明書を発行し、電子ファイルに付与されたeシールを検証することで組織の正当性を確認できます。eシールは大量かつ迅速に発行が可能で、請求書や領収書といった膨大な数が発行される文書で役立つため、企業での導入が進んでいます。
関連内容はこちら
脱ハンコや働き方改革を妨げる「日本のハンコ文化」
政府が脱ハンコを推進しているものの、押印慣行の見直しや廃止はスムーズにいっていないのが現状です。日本のハンコ文化は、政府が掲げる「働き方改革」の推進を妨げる原因のひとつにもなっています。ハンコや押印は古くからの商習慣として日本に浸透してきました。押印は自分の意思決定を明確にし、その内容に責任を持つ証拠となるものです。特に、重要な契約や届け出の際には、押印がないと不備があるとして書類を受け付けてもらえません。
このような慣習により、ほとんどの業務でテレワークが可能になったにもかかわらず、契約書や請求書、決裁のハンコを押すためだけに出社しなければならない場合もあります。コロナ禍でステイホームが強く呼びかけられた時期にも、ハンコを押すだけの「ハンコ出社」や、押印ができないために業務が滞留するケースが見られました。そこで前述のように、現在行政や企業では、このハンコ文化を変革し、より自由に働けるようにすべく「脱ハンコ」の施策を進めています。
ペーパーレスの妨げにも
脱ハンコが進まないと、ペーパーレスも滞ります。ペーパーレスおよび脱ハンコをいち早く取り入れた企業がある一方で、古くからの商習慣の伝統を重んじる企業もあります。
ペーパーレスが進まない原因にはさまざまな理由があります。従来どおり紙の書類として残すことに不便を感じていない、手元にあったほうが安心、ペーパーレスにコストがかかる、社員全員の理解を得るのが難しい、などが主な理由のようです。また、社員のITリテラシーに差がある場合、現場に広く浸透するにはハードルが高いと感じ、デジタル化やIT化を断念する企業もあるようです。
自社でペーパーレスを進めたくても、取引先の抵抗により移行ができないケースもあります。そもそもテレワークを実施していない企業はハンコ出社とは無縁ですので、脱ハンコやペーパーレスに関する意識そのものが低いようです。取引先がそのような状況の場合、理解を得るのが難しいこともあるようです。
脱ハンコのメリット
脱ハンコを進めることにより、企業は無駄な作業を減らせます。さらに文書を電子化することで、より多くのメリットを享受できます。一般的に得られる脱ハンコ・文書電子化のメリットについて以下に紹介します。
コスト削減
ペーパーレスにより、用紙代、封筒代、インク代、プリンターのメンテナンスにかかるコストが不要になります。課税対象の文書なら印紙を貼付する必要がありますが、電子契約なら印紙税を納める必要がないため印紙代も不要です。
契約書を印刷、封入、郵送するための人件費や郵送費なども削減できます。また、紙ベースのときにかかっていた、書類保管スペースや管理に関するコストもカットできるでしょう。
業務効率化
紙の契約書を発行・送付するには、入力、印刷、封入、郵送などの一連の作業に数日かかるケースも珍しくありません。相手先からの返送にも数日かかるため、契約締結までには多くの日数を要します。その点、電子契約ならすべてがオンラインで完結するため、スピーディーに処理が可能です。
後日、契約関連の書類を探す際も、電子ファイルであれば圧倒的に検索しやすく便利です。また、オフィスワーク以外のテレワークでも業務が滞らずに済むのもメリットです。例えば、コロナ禍以降対応に迫られているリモート監査業務にも有用です。
コンプライアンス強化
紙の契約書で保管していると、管理方法を徹底しても保管漏れや紛失、改ざん、コピーなどのリスクをなくせません。電子化してBoxのようなコンテンツ管理システムを利用すれば、セキュリティ高く守られて情報ガバナンス強化につながります。紙は誰が閲覧したかも、コピーされたかもわかりませんが、ITで管理すればアクセス履歴や修正履歴といった証跡が残り、コンプライアンスの徹底にもつながります。
脱ハンコのデメリット
脱ハンコを進め、文書の電子化を行うことにはさまざまなメリットがありますが、まだ現状、難しいと感じる点もあるようです。以下に、障壁となり得るもの、障壁となっている例を紹介します。
電子契約対応できない書類がある
大抵の契約ではペーパーレスが認められ、電子サインで契約(電子取引)ができるものの、たとえば、公証人の面前で作成する義務がある公正証書は、書面での契約が必須で電子サインでの対応ができないなど、電子ファイルや電子サインでの対応が認められていない契約書や申請書もあります。理解を深めるため、具体例として2022年末時点での電子契約が可能な契約と、対応できない契約の代表的なものを挙げてみます。
【電子契約が可能】
- 商業登記・法人登記申請
- 秘密保持契約
- 登記事項証明書及び印鑑証明書の交付申請
- 業務請負契約
- 課税(非課税)・納税証明書申請
- 代理店契約
【電子契約が不可の書類】
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
- 特定商取引(訪問販売等)の契約等書面
業務フローの変更が必要
電子契約や承認申請業務などの脱ハンコを目指してペーパーレス化する場合は、社内の従来の業務フローを見直す必要があります。紙の書類の作成や郵送に携わっていた従業員からは少なからず反発を招くかもしれません。人員削減のための施策ではないことを説明し、理解を得ることが重要です。
また、取引先にも前もって十分な説明が必要です。説明しても取引先からの理解と協力が得られなければ、紙とデジタルデータの2本立てで業務が進行する二度手間になってしまい、負荷があがります。
脱ハンコの推進方法
脱ハンコに向けて紙文書の電子化に取り組む際には、押さえておきたいポイントがあります。以下の手順で実施するとスムーズに進みます。
電子化させる範囲を決める
はじめに、社内で管理している紙文書のうち、どれを電子化するかを決定します。選別を行わずにすべての文書を一度に電子化しようとすると、手間や時間が余計にかかるだけでなく、重要なものとそうでないものが混在してしまい、後から整理する手間がかかります。
また前述したように、制度上まだ電子化対応できない書類も存在するため、法律面にも注意し選別することも必要です。効率化のための脱ハンコが、非効率をもたらしては元も子もないため、慎重な精査が必要です。
社内ワークフローを見直す
文書の電子化により業務効率化ができるかどうかも電子化する範囲を選定する際に役立ちます。そのため、事前に社内のワークフローを明確にしたうえで、文書の電子化により改善が可能なプロセスを洗い出します。場合によっては、社内ルールの策定や変革、ワークフローのデジタル化も併せて実施しましょう。
取引先に事前確認を取る
決定した範囲で文書の電子化を行う前に、取引先に対して今後請求書や契約書などの文書を電子化する旨を通知し、相手の同意を得ましょう。取り組みの経緯や導入メリットなどを伝えると理解を得られやすくなりますが、取引先によっては紙の文書を求めてくることもあります。その場合に備えて、イレギュラー対応を行うなどの対応策も社内で決めておくようにしましょう。
社内への周知を行う
社員に対して文書の電子化について通知し理解を得ることに加え、併せて電子ファイルでの情報管理となることを考慮して、社員に対するデジタルセキュリティ教育を実施することも重要です。情報漏えいの原因の多くはマルウェア感染や不正アクセス、メールの誤送信など、人的要因に由来します。万が一の事態が発生しないように、あるいはセキュリティ事故が発生した際に被害を最小限に抑えられるように、社員のセキュリティ意識を向上させる取り組みが必要です。
関連内容はこちら
脱ハンコ促進に役立つ機能
脱ハンコ・文書のデジタル化を進める際に役立つ機能を紹介します。代表的なものとしては、コンテンツ管理システムや電子サイン、ワークフローシステムなどが挙げられます。
ワークフローシステム
ワークフローシステムとは、従来紙で行っていた申請手続きをオンライン化し、起票から承認、決裁までの一連の業務を行えるシステムです。もう少し平易な使い方だと、電子ファイル化された文書の回覧もあります。導入により入力チェックの自動化や決裁時間の短縮、どこにいても起案、承認できるといった効果が期待できます。
ワークフローシステムは、業務効率化だけでなくコンプライアンスにも有効です。事前に設定した承認経路で処理が行われるため、改ざんしにくくなるほか、誰が承認したかといった履歴が残るため透明性も確保されます。製品によっては、そのまま画面上で印影を表示でき、電子的に捺印できる電子印鑑が利用できるものもあります。
コンテンツ管理システム
電子化された文書、つまり業務コンテンツを管理する際に役立つのがコンテンツ管理システムです。導入によりアクセス権管理やリテンション管理などの機能を使い、文書を適切に管理・保存できるほか、必要なときには検索ですぐに見つけられるようになります。また、蓄積したデータを分析してナレッジとしても活用可能です。こちらもコンテンツ管理の延長線上で電子サインが使えるものがあります。契約書を作成し、電子サインで契約を締結し、そのまま法定保存をするといった使い方です。
電子印鑑
電子印鑑とは、ハンコの印影をデータ化した画像のことです。作成するにはいくつかの方法があります。実際紙に押印したものをスキャンして取り込んで画像にする、イラスト作成ソフトやオフィスソフトの図形描画機能を使う、電子印鑑作成ツールを利用するなどです。電子印鑑作成ツールにも、無料で利用できる簡単なものから、印影のデータに識別情報(シリアル番号など)が含まれるものまであります。
電子化した書類の好きな位置に印影を配置することができ、各種の書類のペーパーレス化に貢献します。書類の作成と同時に押印が完了するため、手作業で押印していた工数を減らせます。印影がかすれたり曲がったりといった失敗もなく、用紙を無駄にすることもありません。
無料ソフトやスキャンして取り込む、図形描画機能を使うといった方法は、印影をコピーして不正利用される危険性もあるため、重要書類に適用すべきではありません。とはいえ、主に社内の稟議書や回覧などに、ゴム印や認印の代わりとして使えます。また、相手方が了承していれば、請求書にも使用可能です。請求書には印影が印刷されているものも多くありますし、請求書の押印は法律上必須ではないためです。
一方、識別情報が含まれるタイプの電子印鑑は、契約書や納品書など社外用にも使用できます。電子サイン法第2条の「本人が作成したものであること」や、「改変されていないこと」を証明できるからです。ただし、実印が必須の不動産登記などには使用できず、実印と同等の効力はありません。
電子サイン
「電子サイン」は、自社発行の正式な書類であり、改ざんされた不正な書類ではないことを証明するためのものです。電子印鑑の項目で言及した電子サイン法第2条の要件を満たすものを指します。作成者や改ざんの有無がわかりにくい電子文書の欠点を補うために作られました。内容に「公開鍵暗号」を用いることで情報漏えいを防ぐため、セキュリティ面でも優れています。
国が定めた電子サイン法では、国指定の認証局により電子証明書を発行してもらうことで、「電子サインが実在する人物の正式なものである」ことの証明になります。その他、タイムスタンプを押してその時刻には当該文書が間違いなく存在し、その時刻以降は改ざんされていないことの証明ができます。
このようにして、電子ファイルでも紙の契約書と同様の効力を持つことになるのです。このような手続きを踏んだ業務ファイルなら、相手先にも安心感を与えられるでしょう。
文書の電子化を行う際には、単純にシステムの導入や紙文書のPDF変換で紙を電子ファイルにするだけでは十分ではありません。ワークフローの最適化による業務効率化や電子サインによる契約締結、真正性の確保、検索性が高くセキュリティの対策もされたコンテンツ管理システムの活用を並行して進めることで、業務全体がデジタル化され、より業務が効率化され、生産性が向上します。その前段として文書の電子化を行い、ペーパーレスを推進することが、脱ハンコならびに業務のデジタル化を実現することにつながります。
より効率的に脱ハンコを実現するためのツール
脱ハンコを実現するツールはさまざまなものがあります。前項で紹介した脱ハンコ促進に役立つ機能を含め、多機能なコンテンツクラウドを活用しながら効率的に脱ハンコの実現を目指せます。
- Box Sign
Box Signは、コンテンツクラウド「Box」が提供する電子サインサービスです。Businessプラン以上のBoxユーザーなら、追加費用なく利用できます。 - SalesforceやUiPathといった主要なアプリやカスタムアプリとも連携でき、シームレスに業務コンテンツでの電子契約を可能とします。営業部門であれば、契約締結までの時間を短縮して営業効率を上げ、人事部門であれば、採用プロセスを効率化し、迅速な意思決定をサポートします。
- 契約ファイル管理
Boxを活用すれば、デジタル化した契約書の管理も効率化できます。契約書の作成から共有、編集、サイン、法定保存、さらに法定保存期間を過ぎたものの戦略的な破棄までの全ライフサイクルを一つのコンテンツクラウドサービスでまかなえ、デジタル契約業務のハブとなります。すべての電子契約を集約させることで、フォルダやファイル管理、コラボレーションやワークフロー、検索の利用も可能です。また、アクセス権限を設定することで、不適切なアクセスを防げます。 - クラウドサイン for Box
クラウドサイン for Boxは、電子契約サービスのクラウドサインとBoxを連携したソリューションです。Boxに保存されている契約前のドラフトを相手に送信し、クラウドサインによって電子契約を締結することが可能です。契約文書はBox内で一元管理でき、いちいち別のシステムのファイルにアクセスする必要がなくなるため、業務効率化につながります。 - お客様事例|シヤチハタ株式会社
印章・スタンプ等のメーカーであるシヤチハタとBoxも連携して電子印鑑サービスを提供しています。ユーザーは自分の名前を入力するだけで、電子文書で使用するハンコの印影をシヤチハタが作成・提供してくれるため、わざわざスキャンするといった手間が省けます。いままで築いてきたノウハウを生かし、入力された名前から業務用に適した印影の作成が可能です。
その他、BoxはDocuSignやAdobe Signとも連携しており、幅広い電子サイン、電子契約ソリューションと連携します。
まとめ
紙文書じゃなくても、押印がなくても法律上問題のない文書はたくさん存在します。それでも長く続いたハンコ文化を変えるのは容易ではありません。しかし、紙文書の電子化、電子印鑑や電子サインの利用といった形で脱ハンコを推し進めると、さまざまなメリットがでます。移行期間は社内や取引先の理解を得る必要があるなど、一定の手間と時間がかかりますが、働き方が変わる、電子帳簿保存法への対応にもつながるなど、メリットの方が多いと感じられるはずです。
脱ハンコの目的は、単に紙や押印を廃止して効率化を行うことだけではありません。さまざまな手続きをデジタル化することで利便性の向上や業務フローの効率化を進め、DXにつなげることにあります。社会の流れが業務のデジタル化・脱ハンコへと向かうなか、従来の紙ベースの書類運用を見直し、ITツールを活用しつつ効率的に文書のデジタル化を進めていくことが重要です。これから脱ハンコに取り組もうという企業は、本記事で紹介した取り組み方や役立つ機能をぜひ参考にしてください。
- トピックス:
- 働き方改革
- 関連トピックス:
- 働き方改革